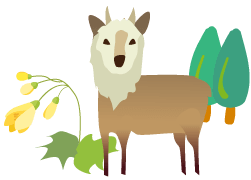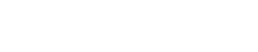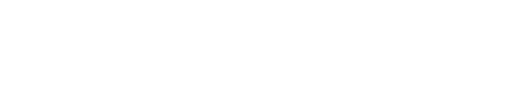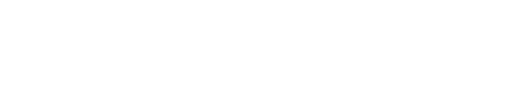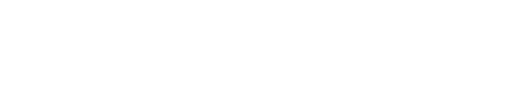〈前編〉草原に息づく小さな命を守る「五ヶ所高原」

熊本県と大分県との県境に接する高千穂町。その北部に位置する「五ヶ所高原」は、平均標高800mを超える草原地域です。
1年を通して冷涼な気候にあり、県内ではなかなかお目にかかることができない希少な植物や昆虫の棲みかであることでも知られています。しかし情勢の変化などにより、これらの生き物たちはいま、絶滅の危機に追い込まれているのです。
思い出の中にある、オレンジ色の景色

ふるさとの小さな命の灯火を消さないためにと、長年にわたり環境省の自然公園指導員を務め、現在も『五ヶ所高原 ゴマ姫の草原を守る会』の会長として精力的な活動を続けている甲斐英明さん。
同会の名称にある「ゴマ姫」とは、五ヶ所高原に生息する代表的な植物や昆虫のことを指しています。
同会発足のきっかけとなったのは、五ヶ所が自生の南限とされ、6月下旬から7月上旬ごろに可憐なオレンジ色の花を咲かせる「ヒメユリ」の存在です。
この場所で生まれ育ち、進学と同時に一時は地元を離れた甲斐さん。数十年ぶりに帰郷した時には、幼い頃ふつうに目にしていたヒメユリの群生は見る影もなくなっていたといいます。
「国内に点在する自生地のほとんどは採集を禁止する条例がすでに制定されていたため、多くの愛好家たちが五ヶ所に集中して訪れ、持ち帰られてしまっていたようです」
危機的な状況を悟った甲斐さんは野生動植物保護監視員に名乗りを上げて本格的に保護活動を始め、さらに平成23年には地元の同志に声を掛けて同会を立ち上げました。

ヒメユリは現在、宮崎県の希少野生動植物に指定されている。「自家増殖した株は交雑種である可能性が高いため、持ち込んでもいけない」と甲斐さん。
また、活動中に宮崎昆虫調査研究会の岩﨑郁雄さんとの出会いがあったことで、県内ではここにしか生息しない蝶『ゴマシジミ』と『ヒメシロチョウ』の存在を知った甲斐さん。協力して調査を行った結果、エサとなる植物・ワレモコウやツルフジバカマが動物の食害にあっており、それが原因でこれらの昆虫たちも急激に減少していることがわかりました。
以来、同会はシカやイノシシの侵入を防ぐ防護ネットの定期的な設置・修繕を実施。ほかにも、大切な繁殖地である広大な草原の保全のために火入れや草刈りを行うなど、やるべきことは尽きません。

ゴマシジミの写真。ワレモコウと呼ばれる多年草に産卵し、孵化した幼虫は地上に下りる。そしてアリが好む化学物質を出して巣に運ばれ、アリの幼虫を食べて成長するという特殊な生態をもつ。

ヒメシロチョウの写真。ツルフジバカマが唯一の食草であるため、獣害対策は必須。
これらの蝶も平成26年に県の希少野生動植物に指定されたことにより、採取・捕獲は禁止されています。五ヶ所高原を訪れ、運良く希少な生き物を目にした際は、決して触れることなく自然の中のありのままの生態を観察してください。
ふるさとの未来を見つめ続ける

長年の功績が称えられ、自然公園関係功労者環境大臣表彰を受賞した経歴もある甲斐さん。しかし、まだまだその勢いは止まらない。
甲斐さんらの活躍により盗掘や捕獲は減ったものの、命を再び増やすことは難しく、現状を維持するだけでも大変な根気と労力が必要です。
平成22年には町立五ヶ所小学校が閉校するなど、過疎化が進むこの地域では、同会に所属している会員たちの高齢化も目下の課題。今後も活動を継続するため、甲斐さんの奮闘は続きます。
「昨年設立したばかりの『高千穂町まちづくり公社』と連携し、町外から協力者を募り、草原の草刈りや防護ネットの設置を行うイベントを企画しています。まだ試験段階ですが、今後さらなる展開を目指したい。単に人手を確保するだけでなく、そうやって徐々に交流人口を増やし、ここにしかない魅力を多くの人に知ってもらえたらうれしいですね」と笑顔で語ります。
五ヶ所の歩みを見つめ、常に自ら行動を起こし続けてきた甲斐さんだからこそ、ふるさとの未来にかける想いは熱く燃え続けています。