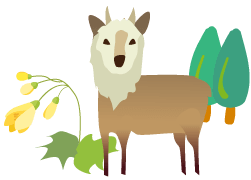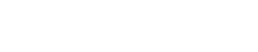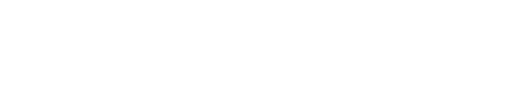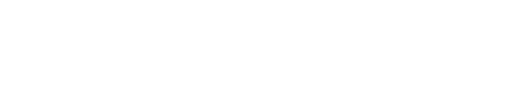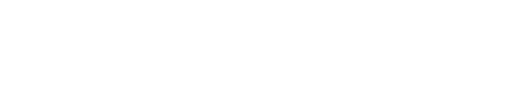顔に墨を塗り、安全祈願——鉱山集落で400年続く奇祭「木浦すみつけ祭り」

「ひとつ祝わせちょくれ」
そう声を掛け合いながら、墨を付けた大根の切れ端を手に取り、次々とお互いの顔に墨を塗りつけていく人々。
これは、“奇祭”と呼ばれる「木浦すみつけ祭り」を象徴する光景です。
佐伯市宇目にある木浦鉱山で隔年2月に行われる祭りで、山の神を祀る山神社の境内は、数百人もの群衆の熱気で満たされます。

県内外から訪れた参加者でひしめく山神社の境内。
木浦鉱山はかつて国内有数の銀山として名を馳せ、その歴史は古く、一説には保元二(西暦1157)年に拓かれたといわれています。
1600年代に鉱山の繁栄と坑夫たちの無病息災を祈願する神事を執り行っていたのが祭りのはじまりとされ、のちに娯楽のエッセンスが加えられ、現在のかたちへ発展を遂げたとされています。
“すみつけ(墨つけ)”の由来には諸説あり、「かつて落盤事故が起こった際、顔に墨をつけて遊んでいて助かった若い男性がいて、それにあやかったため」という説や「銀鉱石が墨のように黒く、銀が多く産出されるよう願いを込めたため」という説などがありますが、いずれの伝承も鉱山集落ならではといえます。
栄華を誇った昔に思いを馳せる
同祭りはまず神事に始まり、次に民謡「宇目の唄げんか」をはじめとする伝統芸能の披露が行われます。
木浦鉱山の地域風俗や鉱山作業の様子を映し出した歌詞からは、この場所がもっとも栄えた当時の情景を思い浮かべることができます。
●宇目の唄げんか
木浦鉱山へ働きに出た夫婦のもとに「子守奉公」として集められた娘たちの唄が原型とされる民謡。対話形式で繰り返される攻撃的な歌詞が特徴で、日々の子守のつらさを唄にぶつけざるを得なかった娘たちの心境が伺えます。
—続いて今度は、荒神が境内に舞い降り、ステージに上がって演舞を行います。


赤い装束と面を身につけた荒神が、威勢のよい掛け声とともに披露する舞は一見の価値あり。
荒神舞が終わると、いよいよ墨つけ。
赤ん坊にお年寄り、観光客や警察官にまで、だれかれ構わず墨が塗られていき、境内は参拝者の笑い声で溢れます。


参拝者の顔が黒く塗られたら、境内を飛び出し、山の神を表現した高さ約5mの大幣を先頭に、荒神たちが集落の家々を回ります。
荒神が各戸に上がり、住民たちの顔にも墨を塗って一人一人の無病息災を祈願するのです。


訪問を受けた家は、簡単な酒肴を用意してもてなすのがならわし。
伝統の火を未来につなぐ
木浦鉱山は17世紀後半に最盛期を迎えるも、その後は徐々に衰退し、1945年の終戦とともに休山。
かつては遊郭や芝居小屋が軒を連ねるほど栄えていましたが、今では当時の面影はほとんど残されておらず、佐伯市指定文化財の「女郎の墓」や旅館や商家の廃墟が、以前の町並みや人々の生活ぶりをわずかに伝えてくれます。
過疎・高齢化も進み、同祭りも一時は中止に追い込まれましたが、地元出身者の協力により、再び伝統の火が灯されました。
普段はもの静かな山村の風景ですが、2年に一度やってくるこの日ばかりは、かつての賑わいを取り戻したかのよう。
鉱山の歴史や人々の暮らしの変遷に、思いを馳せずにはいられません。
この伝統が、これからも脈々と受け継がれていくことを願ってやみません。